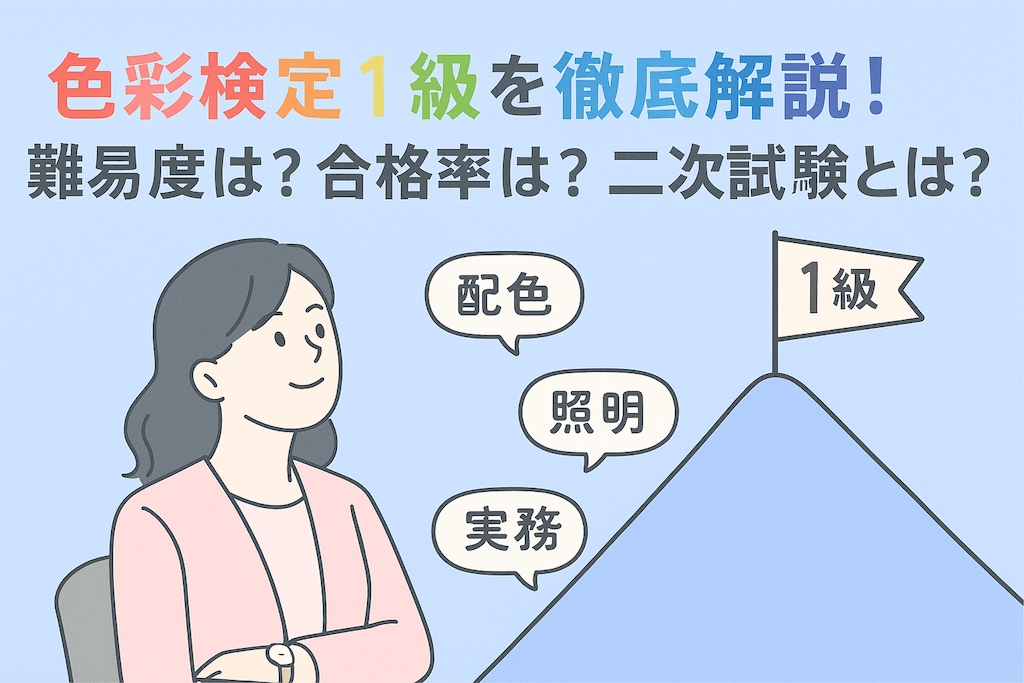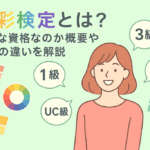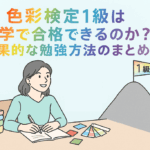「色彩検定1級、挑戦したいけれど難しそう…」「一次だけでなく、二次試験もあるって本当?二次試験は何をするの?」「独学で通用するのかな…」などなど、不安や期待を抱えるあなたへ。1級は、色彩を専門的に扱う「色のプロ」を目指す人の登竜門です。ここを突破すれば、配色提案、空間設計、ブランド戦略など、仕事や副業で実力を発揮できるようになります。色を扱う仕事への就職面接時にも、大きなアピールとなるでしょう。
このガイドでは、1級の難易度や学習内容、一次・二次試験の構成、合格率、そして資格の活用メリットを徹底解説します。「色を本気で学びたい」と思うあなたに、選ばれる理由と自信を届ける記事です。
色彩検定とは?
色彩検定は、公益社団法人色彩検定協会(AFT)が主催し、文部科学省の後援を受けている信頼度の高い資格です。級は3級〜1級の3段階と、ユニバーサルカラーについて専門的に履修するUC級があります。1級は色彩のプロフェッショナル向けの最高峰レベルです。色彩検定そのものについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【関連記事】「色彩検定とは?3級・2級・1級・UC級の違いと難易度比較」
色彩検定1級の試験概要|一次試験・二次試験の違いとは?
1級の試験は「学科試験(一次)」と「実技・論述試験(二次)」の2段階構成です。試験の概要と、一次・二次試験の違いを見ていきましょう。
1級の試験は冬期のみ開催(重要)
色彩検定の試験は年2回、夏期(6月)と冬期(11月)に実施されます。ただし、1級の試験は冬期のみ受験できます。夏期は3級、2級、UC級のみ、冬期は全級が対象です。そして、11月に1級1次試験を合格した方は、12月に実施される二次試験に進むことができます。
一次試験:マークシート式の学科試験
一次試験は、配色理論・色彩調和・視覚特性・照明・色彩史など広範な知識がマーク式で問われます。制限時間80分で80〜120問前後の出題で、60%以上正答が合格ラインです。実務でも必須の視覚理論や国際規格を深く理解しているかを測る試験です。幅広い分野をまんべんなく学ぶことがポイント。
二次試験:記述式+実技の構成
二次試験では、目標の配色提案や論述、実測する実技などを通じて「色を扱う実務能力」が問われます。試験時間は90分です。
- 記述試験:配色理由、光源や素材との関係など緻密な思考力を文章で説明
- 実技(配色提案):設問に対し、色票を用いて、目的に応じた配色を作成します。配色の意図や使い方を他者に伝える技術が問われます。
一次試験の免除について
一次試験に合格したものの、二次試験で不合格となった場合や、病気や都合など何らかの事情で二次試験を受験できなかった方は、その後2年間一次試験が免除されます。
たとえば、2023年に一次試験に合格して同年の二次試験で不合格だったなら、2024年、2025年は一次試験が免除され、二次試験の合格のみで1級の認定を取得できます。(ただし、試験の申し込みは必要です)
ほかの級と併願できる?
色彩検定1級と2級、3級、UC級は併願が可能です。試験時間は重複しないようになっていて、3級の試験は午前、2級、UC級、1級は午後です。
2024年冬期の色彩検定各級の試験開始時間は、3級が10:00 ~ 11:00(60分)、2級が12:00 ~ 13:10(70分)、UC級が13:50 ~ 14:50(60分)、1級1次が15:30 ~ 16:50(80分)という構成でした。
朝から長丁場となりますから、集中力の維持が大変です。特に1級は最後のため、全級の併願は可能であっても1級だけに絞ってチャレンジしたほうが良いかもしれません。
検定受験料・申込方法
1級の試験受験料は15,000円です。一次試験免除者で、翌年以降に二次試験だけを受ける方も同額です。
受験の申し込みは、協会の公式サイトからおこないます。例年、試験開始の3ヶ月ほど前から1ヶ月前(8月~10月)ごろに申し込みできます。余裕をもって申請しましょう。申し込みが済めば、試験開始の10日ほど前までに受験票が届きます。なくさないように保管して、当日、指定された試験会場に持参してください。
色彩検定1級の出題範囲と学習内容を詳しく解説
1級は、色の深く専門的な応用力を身につける学びの場です。色彩を扱うプロフェッショナルとして、幅広い知識を履修します。以下、その一部をご紹介しますね。
3級・2級よりも深い色彩理論と実務的応用
1級では、以下のような知識を学び、試験で出題されます。
一見すると出題範囲としては多くないように思えますが、これらの各領域を深く掘り下げて、専門知識と専門用語を理解しなければなりません。
論述・応用問題への対応力も問われる
記述式では、「ある空間を◯◯ターゲットに対して配色せよ」「なぜその配色を選んだのか」のような問いが出ます。配色の選択理由を、色彩学・心理効果・ユニバーサルカラーを踏まえて論理的に説明するアウトプット力が求められます。
これに対応するためには、事前に「配色ディスカッション」やプレゼン練習、つまりインプットではなくアウトプット型のトレーニングがとても効果的です。文章作成力も、合格には不可欠。繰り返し練習しましょう。
色彩検定1級の難易度と合格率は?
1級は「難関資格」と言われる所以があります。数字で確認してみましょう。
合格率の推移と数字で見る難しさ
- 一次試験合格率:約30〜40%
- 二次試験合格率(最終):約15〜20%
一次通過者は全体の約三割前後、最終合格者は二次合格基準の厳しさもあり、5〜8人に一人程度と非常に狭き門です。
一次試験も二次試験も、合格ラインは200点満点の140点前後。開催年ごとの試験の難易度によって若干の変動はありますが、6割を正解すれば合格です。
どんな人が合格している?求められるレベル感
合格者には、デザイナー・インテリアコーディネーター・教育関係者など、色を実務で扱う人が多い傾向です。また、独学や専門学校で学んできた人の両方が合格していますが、「実務経験+論理的配色力」が合格を後押しする鍵となっています。
色彩検定1級は独学で合格できる?
独学については、別記事で詳しく解説する予定ですが、概要をまとめます。1級の独学合格は可能です。私自身、独学で合格しましたから。
ただし、学習の計画性と実践練習が必要不可欠。市販の参考書や過去問・模擬試験、配色練習、プレゼン準備などを含め、最低半年〜1年の学習期間を見ておくのが安心です。
色彩検定1級を取得するメリット
1級取得によって広がる可能性と仕事での活用ポイントを見ていきましょう。
就職・キャリアアップに活かせる
1級を持つと、企業が色彩を「強み」にしている部署や職種で特に評価されます。
「色の専門家」として肩書きを得ることで、プレゼン力や提案力も格段に向上します。
色彩の専門家として自信を持てる
1級を取得すれば、単なる色好きではなく「理論を根拠に発信できるプロ」として自分を名乗れます。講師活動、執筆メディア、カラー監修などの機会が開け、色彩に関わる上での自信が自然と深まります。
まとめ|色彩検定1級は努力の価値あり!
色彩検定1級は、難易度も高く合格率も低いですが、そのぶん価値も大きい資格です。学科+実技という実務対応力が試される構成のため、理屈・実践・アウトプットが求められます。でも、その先には「色の専門家」としての自信と仕事の広がりが待っています。
「色彩検定1級」という一歩を踏み出せば、色を通して自分自身も成長できる。ぜひ、あなたの挑戦を応援しています!