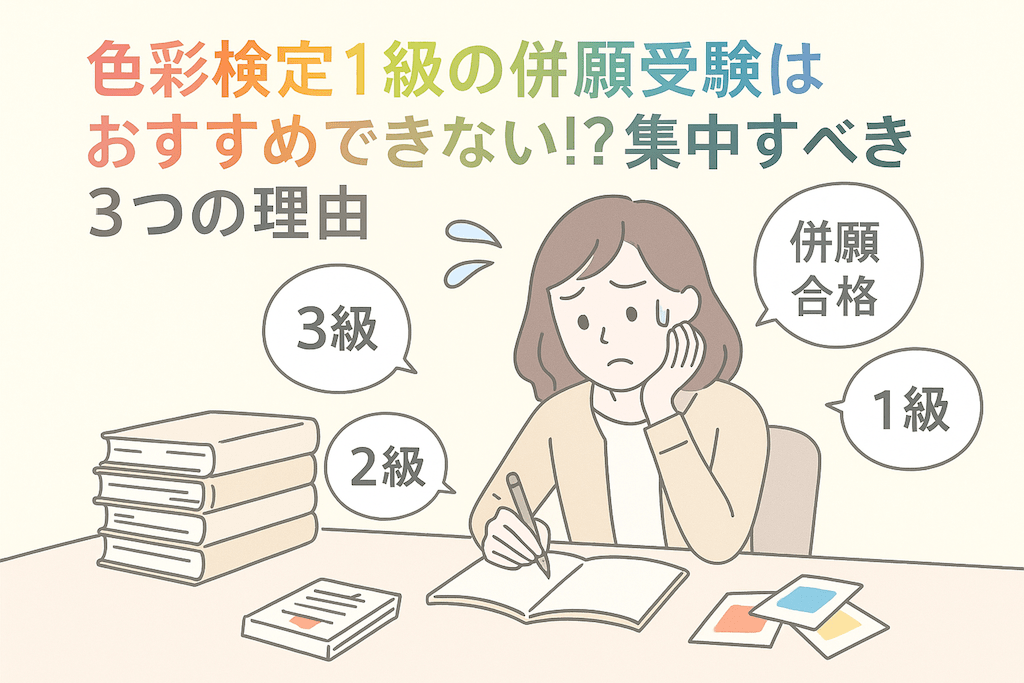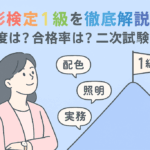「色彩検定1級を受けたいけれど、せっかくなら2級や3級と一緒に受験してしまおうかな…」
「試験会場に行く手間も減らせるし、効率がいいんじゃない?」
こう思ったことはありませんか?
色彩検定には複数の級を同日に受験できる「併願制度」があります。特に1級を目指す方のなかには、「2級や3級をまだ取っていないから、一気にまとめて受けてしまおう」という発想になる人も少なくありません。
確かに、併願受験には一見メリットがあるように見えます。しかし実際のところ、色彩検定1級は学習範囲が膨大で、出題レベルも非常に高く、併願によって合格率を下げてしまうリスクがあります。
本記事では、色彩検定1級における併願受験の仕組みや注意点、そして「なぜ単願で集中すべきなのか」という理由を、経験者の声や試験データを交えながら詳しく解説します。
色彩検定とは?1級の概要を簡単におさらい
色彩検定は、公益社団法人 色彩検定協会(AFT)が実施する、色彩に関する知識・技能を認定する資格です。インテリア、ファッション、広告、商品企画など幅広い業界で評価され、就職・転職にも有利になる資格として知られています。
1級はその中でも最上位に位置する級で、合格することで色彩の高度な専門知識と実践力を証明できます。
1級試験の特徴
- 試験形式:一次試験(マークシート+記述)と二次試験(配色実技)
- 出題範囲:色彩史、光と色、色彩心理、色彩調和論、照明、ファッション・インテリア・商品色彩計画、色彩法規 など
- 合格率:例年30%前後(一次・二次両方の合格が必要)
- 試験日程:年1回(11月に一次試験、12月に二次試験)
詳細は「色彩検定1級を徹底解説!難易度は?合格率は?二次試験は何をする?」の記事でさらに詳しく紹介しています。
色彩検定1級の併願受験とは?
次は色彩検定の併願制度についてご説明します。
併願受験の仕組み
色彩検定では、同一試験日に複数の級を受験できる併願制度があります。色彩検定の試験は級ごとに開始時刻が分けられていて、受験申込(願書)の提出時に複数の級を選択すれば、同じ日にそれぞれの級を受験できます。
そもそも色彩検定試験は、夏期(6月)と冬期(11月)の年2回実施されます。ただし、一級は冬期のみの実施です。よって、他級と一級の併願受験できるのは冬期だけ。たとえば、2025年の冬期試験は以下のスケジュールです。
3級は午前、2級は昼から。UC級を挟み、1級は一番最後の開始となります。
併願を選ぶ理由
- 効率的に資格を取得できる
複数の級を短期間で取得し、履歴書やポートフォリオに早く反映させたい人にとって魅力的です。 - 受験料や交通費を節約
試験会場への移動や宿泊を一度で済ませられます。 - 学習モチベーションの高いうちに受けたい
勉強の勢いがあるタイミングで一気に挑戦したい場合もあります。
色彩検定1級で併願受験をおすすめしない3つの理由
併願制度があるものの、1級と他の級の併願は、よほど十分に勉強時間を確保できない限りはおすすめできません。併願をおすすめしない主な理由を3つご説明します。
理由1:学習範囲が膨大で時間不足になりやすい
1級は2級の知識を前提としつつ、さらに専門性を高めた出題がされます。色彩理論では光の波長や分光分布、視覚特性、色の物理的測定方法まで求められ、配色問題では複雑な条件に沿った提案力が試されます。
併願では、1級に加えて他の級の学習もしなければなりません。たとえば、1級と2級の併願を選んだ場合、以下のような時間配分になります。
例:試験まで4か月の場合の理想的な学習時間配分(1級単願)
- 平日1〜2時間、休日4時間程度の学習で合計300〜400時間
- 全て1級対策に充てる
併願の場合
- 1級:全体の70%程度
- 2級:全体の30%程度
→ 1級対策時間が単願より約100時間減少
これだけで合格可能性は大きく下がります。特に働きながら勉強する社会人や、学業と両立する学生にとっては、時間不足が致命的になります。
理由2:出題レベルの差が大きく、学習の優先順位が崩れる
2級や3級の試験は基礎〜中級レベルであり、暗記中心でも高得点が狙えます。一方、1級は記述・論述式の出題もあり、理解力や応用力を試されます。
併願すると「覚えやすい基礎分野」に時間を割きやすくなり、1級特有の難問対策がおろそかになります。過去問分析や実技練習など、時間のかかる勉強が後回しになるのです。
特に二次試験の配色実技は、過去問や模擬問題を繰り返して手を動かす練習が必須です。併願によってこの時間を確保できないと、一次試験に合格しても二次試験で失敗する可能性が高くなります。
理由3:試験日程・形式の違いが集中力を削ぐ
併願では試験時間が長時間化します。たとえば午前に3級、昼過ぎから2級、午後15時から1級の一次試験を受けるとなると、朝から夕方まで緊張状態が続きます。
もっとも合格したい1級試験の時点ですでに集中力が低下している恐れもあり、大きなリスクです。また、試験前に他の級を受けてしまうことで、1級対策に特化した「頭の準備」ができないまま試験に臨むことになります。
併願を避けるべきケースと単願が有利なケース
- 勉強時間が1日2時間未満しか確保できない人
- 仕事や家庭の予定で試験直前の追い込みが難しい人
- 1級を1回の受験で確実に取りたい人
- 過去問をまだ一度も通して解いたことがない人
こうした場合は、迷わず単願で1級だけを受験するほうが賢明です。
どうしても併願したい場合の対策例
冬期試験まで十分に時間の余裕があり、2級1級を同時に受けたいと考えるなら、以下の点はぜひ意識しておきましょう。(3級は先に合格している前提です)
1. 学習スケジュールの明確化
- 試験日から逆算し、1級の学習時間を全体の70〜80%確保する
- 併願する級は試験1か月前から集中対策
2. 過去問を軸にした効率学習
- 1級は過去5年分の問題を最低3周
- 併願する級は過去問2〜3年分を重点対策
3. 模擬試験・時間配分の練習
- 連続試験を想定して、実際の時間配分で模擬試験を行う
- 食事や休憩で集中力を切らさない工夫を実践
まとめ:1級合格を最優先に戦略的な受験計画を
色彩検定1級は、合格率が低く学習負担も大きいため、安易な併願は危険です。限られた時間と集中力を1級に注ぎ込み、確実に合格を狙う戦略こそが、結果的に最短ルートになります。
出題範囲が広くて勉強が大変であることと、試験当日に集中力を維持できるかどうか。この2点が併願の難しいところ。色についてまだ全然勉強したことがない、という状態で一気に3級〜1級までの合格を目指すのであれば、夏期に3級と2級を併願し、冬期に1級を受けるなど、分けたほうが無難です。
1級では、11月の一次試験に合格した方のみ12月の二次試験を受けることができます。そして、二次試験をクリアして、ようやく1級の合格となります。もし二次試験にて不合格だった場合、翌2年間は一次試験が免除され、二次試験のみの受験で合否を判定します。(ただし、翌年に改めて受験申込が必要)
この一次試験免除制度はありがたいものの、翌年12月まで1年間モチベーションを維持するのは大変。できるかぎり一発合格を狙いたいところです。そのためにも、無理な併願は避け、単願で確実な成果を狙ってください。
もちろん、どうしても併願する場合は、時間配分と学習優先度の管理を徹底することが必須です。受験スタイルは人それぞれですが、「合格」というゴールから逆算して、最適な選択をしてください。
公式テキストを通読・熟読し、要点を整理して覚え、配色カードを使ってカラーコーディネートの実践を繰り返し、過去問を解く。併願にせよ単願にせよ、この学習方法は変わりません。1級は3級、2級を知識をベースとしますから、1級合格に意識の比重を置きつつも足元の基礎を固めて理解を深めていきましょう。