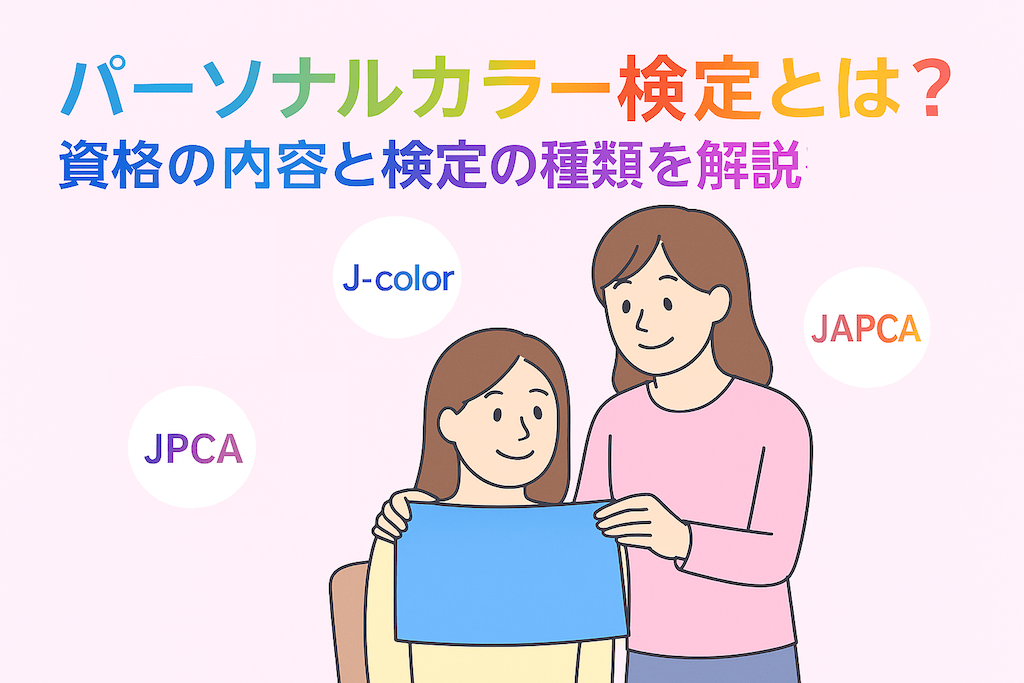パーソナルカラー検定っていくつもあるけれど、結局どれを受けたらいいの?」「就職や副業に役立つのはどの資格?」「趣味で学びたいだけでも挑戦できるの?」
そんな疑問を抱いている方は少なくありません。パーソナルカラーは、ファッションやメイクに欠かせない存在となり、近年は“資格として学ぶ”人が急増しています。しかし、日本には複数の団体がパーソナルカラー検定を実施しており、受験を考える方にとって「違いがわかりにくい」という課題があります。
この記事では、パーソナルカラーの基本概念から、各団体の検定の違い・特徴・選び方までを包括的に解説。自分の目的に合った検定を見つけられるよう、丁寧にナビゲートしていきます。
パーソナルカラーとは?基本の考え方と役割
まずは検定を理解する前に、パーソナルカラーそのものについて整理しておきましょう。
パーソナルカラーとは、人の肌・髪・瞳の色に調和する「似合う色」のこと。色彩心理や視覚効果に基づき、印象を引き立てる色を導き出す概念です。
パーソナルカラーの定義と歴史的背景
パーソナルカラーは20世紀初頭のアメリカで生まれました。特に有名なのは「シーズン分類」と呼ばれる手法で、人を春・夏・秋・冬の4つのグループに分けて、似合う色調を提案します。色をブルーベース(ブルベ)、イエローベース(イエベ)という2つに分類し、さらに春夏秋冬にわける方法が一般的。日本でも1980年代にファッションやメイク業界で注目され、現在は美容師、メイクアップアーティスト、アパレル業界などで欠かせない知識になっています。
なぜ重要?ファッション・メイク・ビジネスへの活用
パーソナルカラーを理解すると、洋服やコスメ選びで失敗が減り、自然に自分の魅力を引き出せます。また、プロとして活動する場合、診断スキルはお客様の満足度を大きく左右します。そのため、検定を通じて「理論的に色を理解し、説明できる力」が求められています。
パーソナルカラー検定とは?資格の目的と概要
ここからは、具体的に「検定とは何か」を見ていきましょう。パーソナルカラー検定は、色彩理論と診断技術を体系的に学べる資格です。
検定で学べる内容(色彩理論・診断スキルなど)
- 色相・明度・彩度といった基本理論
- 4シーズン分類の診断方法
- 顔立ち・髪色・肌色との調和分析
- ファッション・メイクへの応用
- 色彩心理学の基礎
似合う色、似合わない色というのは個人の感覚、好き嫌いのように思えますが、そうとは言えません。調和する色・不調和の色の組み合わせは存在します。検定を通じて、単なる「感覚的な似合う色」ではなく誰にでも説明できる知識として学べるのが大きな特徴です。
取得することで得られるメリット
- 自分に似合う色を見極められる
- 美容やファッションの現場で役立つ
- パーソナルカラー診断士として副業が可能
- 顧客への説得力が増し、信頼を得られる
趣味から仕事まで、幅広い目的で価値のある資格といえるでしょう。
主なパーソナルカラー検定の種類と特徴
日本では複数の団体がパーソナルカラー検定を主催しています。主に有名なのは次の2つです。
色彩技能パーソナルカラー検定(JPCA)

NPO法人日本パーソナルカラー協会(JPCA)が主催する「色彩技能パーソナルカラー検定」は、2003年から実施されている日本で最も古いパーソナルカラーの資格です。
JPCAによるパーソナルカラー検定は、色を四属性(一般的な色相、明度、彩度に加えて、清濁)の観点から分類し、身につける色によって顔や全体の印象がどのように変化するのか、客観的な法則性をわかりやすく学ぶことができるという強みを持っています。
検定制度はモジュール1(初級)、モジュール2(中級)、モジュール3(上級)の3段階。モジュール2までは筆記のみ、モジュール3の最上級では、実際に色を対象者に当てて診断する実技試験を実施します。お客様に提案するにあたっての実用的な知識と技術を習得できます。
- 特徴:美容業界に直結する内容が多い
- 級制度:モジュール1(初級)、2(中級)、3(上級)とステップアップ方式
- 強み:診断技術の習得を重視
- 対象者:美容師、メイクアップアーティストなど現場志向の方
色彩活用パーソナルカラー検定(J-color)

一般社団法人日本カラーコーディネーター協会が主催する「色彩活用パーソナルカラー検定」は、パーソナルカラーの原点から実務に役立つ知識までを履修できる資格です。パーソナルカラーは主催者や提唱者によって幾つかの流派に分かれます。色彩活用パーソナルカラー検定は、それら各流派に共通する理論を、基礎から応用まで幅広く学ぶことができます。
- 特徴:初心者からプロまで幅広く学べる体系
- 級制度:3級(基礎)、2級(応用)、1級(プロ)
- 強み:各流派のベースとなるパーソナルカラーの基礎を学べる
- 対象者:趣味で学びたい方から、キャリアアップを目指す方まで
パーソナルカラリスト検定(JAPCA)

一般社団法人日本カラリスト協会(JAPCA)が主催する「厚生労働省後援 パーソナルカラリスト検定」は、その名のとおり厚生労働省が後押しする資格で、2005年に第一回試験を実施しました。「人と色」に着目した色彩知識と配色調和を身につける資格試験です。同協会が提唱するCUS表色系(カラーアンダートーンシステム)の理論を用いた配色提案ができる人材の育成を目的としています。
- 特徴:CUS表色系に基づく最適な色の提案
- 級制度:3級、2級、1級
- 強み:厚生労働省後援、各種業界団体も支援
- 対象者:仕事で色を扱う・カラリストとして独立を検討している方
その他の団体が実施する資格
このほか、ICBIパーソナルカラー実務検定協会による「パーソナルカラー実務検定」という資格もあります。また、広義では、全日本カラースタイルコンサルタント協会が主催する「イメージコンサルタント」の資格も、パーソナルカラーの領域の資格と言えるでしょう。
このように複数の資格が存在することが「結局どのパーソナルカラー検定を受けたら良いの?」と迷う原因となっています。
しかし、この疑問に対する明確な答えはありません。認知度でひとつ選ぶなら、色彩技能パーソナルカラー検定が最適かもしれません。パーソナルカラーの基礎理論について幅広く学びたいということなら、いくつかの団体の資格にチャレンジしてみても良いと思います。
パーソナルカラー検定の級別難易度と学習内容
ここでは「級ごとにどんな内容を学ぶのか」を整理します。
3級(基礎編:初心者向け)
- 色の基本理論を学ぶ
- 自分のパーソナルカラーを理解する
- 趣味や日常に活かせるレベル
2級(実践力を養う中級者向け)
- 他者の診断方法を学ぶ
- ファッション・メイクへの具体的な応用
- お客様に提案できる力を育成
1級(プロフェッショナル向け:仕事に直結)
- 診断実技を中心に高度なスキルを習得
- 複雑なケースにも対応可能
- 美容業界での即戦力として活躍できる
色彩技能パーソナルカラー検定も色彩活用パーソナルカラー検定もカラリスト検定も、等級が3段階に分かれています。これらの資格はどちらも、初級は基礎、中級は深掘り、上級は実務能力を養う内容となっています。
したがって、どこまで学びたいのかによって目指す等級が変わります。
どのパーソナルカラー検定を選ぶべき?選び方のポイント
ここまで見ると「結局どれを受ければいいの?」と迷う方も多いはず。ここでは選び方を解説します。
目的別(趣味/キャリアアップ/プロ活動)
- 趣味で学びたい方:JPCAの初級やJ-colorの3級
- 副業を目指す方:モジュール2、2級に挑戦
- 仕事に活かす・プロ活動する方:1級を取得して信頼を得る
試験内容・難易度・費用の違い
- J-color:座学と実技がバランス良く学べる、受験料は比較的リーズナブル
- JPCA:実践的な実技重視、ややハードル高めだが美容業界での評価が高い
学びやすさや教材の充実度
独学かスクール受講かによっても選び方は変わります。J-colorは独学に向き、JPCAは講座を通じた実技学習が強みです。(JPCAも独学でモジュール1まで取得可能です)
色彩検定やカラーコーディネーター検定との違い
色彩検定やカラーコーディネーター検定は「色彩全般」を学ぶ資格です。これに対して、パーソナルカラー検定は「人に似合う色」に特化しています。目的が異なるため、棲み分けが可能です。
※詳しい比較は関連記事にまとめていますので、そちらをご覧ください。
まとめ:自分に合った検定を選んで、パーソナルカラーを活かそう
パーソナルカラーという概念自体がまだ比較的新しく、提唱者や主催団体によって考え方に若干の違いがあります。そのために、検定試験がいくつも乱立している、という状況が生まれています。
ですが、どのパーソナルカラー検定も、美容やファッションの世界で役立つだけでなく、日常生活の「色選び」を豊かにします。
検定を受ける動機は「自分に似合う色を探そう」「仕事でお客様に提案するために勉強したい」「パーソナルカラーアドバイザーとして独立起業したい」などさまざまだと思います。
どの検定を選ぶにせよ、ひとつ気をつけてください。学んでいるうちに、いつのまにか似合う色・似合わない色の理論に縛られたり、「私はイエベだから、こんな寒色は似合わない」「あなたはブルベだから、その暖色は微妙」とネガティブに考えてしまうかもしれません。でもそうなると、「パーソナルカラーの知識は、色選びについて学んで、魅力アップするためのもの」という本来の目的からズレてしまいます。
「こういう理由で、この色はあなたの魅力をもっと引き出しますよ」と、説得力を持った言葉を添えられることが、資格取得の最大の利点です。そのための資格取得なんだという原点は忘れないようにしてください。
どの検定も公式テキストを用意しているので学びやすいですが、特に「色彩技能パーソナルカラー検定」は公式テキストや配色カード、実務用のドレープなども販売していて教材面では充実しています。
あなたにあった資格試験を選び、あなたにあう色を探す旅をはじめてみましょう!