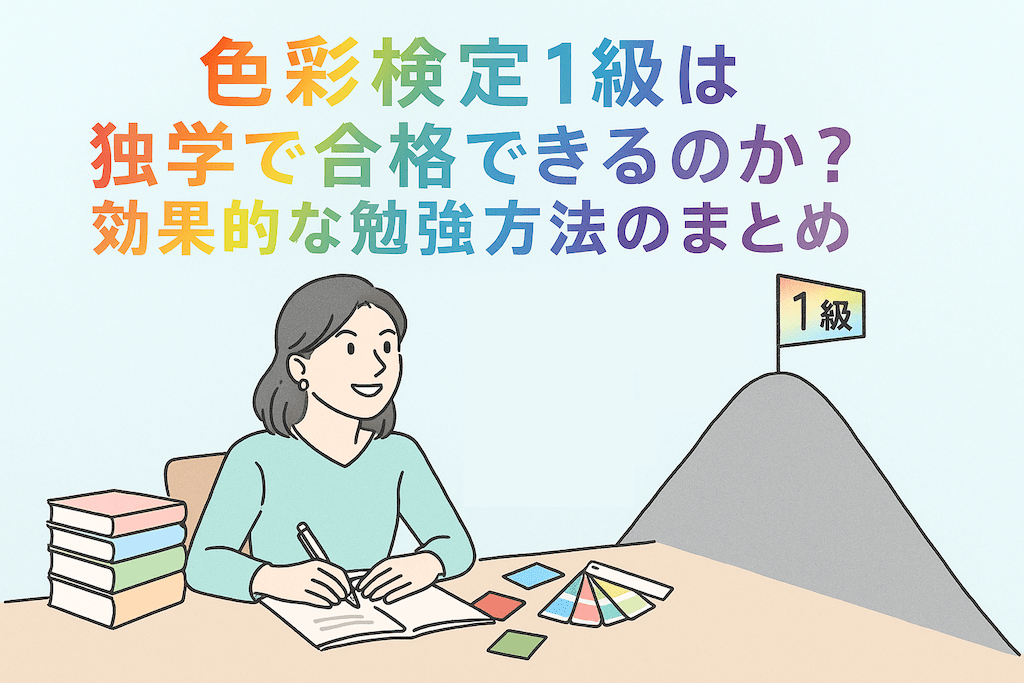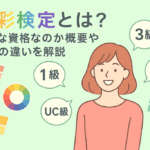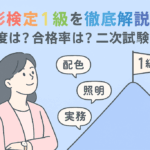「色彩検定1級に挑戦したいけれど、独学でも合格できるのかな?」「通信講座やスクールに通った方が安心?」そんな疑問を抱いている方は多いでしょう。特に、すでに2級を取得して次のステップに進もうと考えている方や、3級・2級と併願して一気に合格を狙う方にとって、1級の難易度や勉強方法は気になるポイントです。
本記事では、色彩検定1級を独学で突破するための現実的な学習スケジュールや効果的な勉強法、注意点を徹底的に解説します。試験合格を目指す方が、自分に合った学習スタイルを見つけられるようサポートします。
色彩検定とは?1級はどんな資格?
色彩検定は、公益社団法人AFT(日本カラーコーディネーター協会)が主催する色彩の知識・技能を問う資格試験です。3級から始まり、2級、そして最難関の1級までステップアップ形式で構成されています。
1級は「色彩の専門家」として認められる水準であり、ファッション、インテリア、デザイン、広告、教育など幅広い分野で役立つ資格です。詳しい試験概要や出題範囲は、別記事「色彩検定1級を徹底解説!」にて紹介していますので、併せてご覧ください。
色彩検定1級は独学で合格できるのか?
色彩検定1級は難易度が高く、多くの受験者が「独学で合格できるのか」と不安になります。結論から言えば、独学での合格は可能ですが、効率的な勉強方法と計画性が欠かせません。ここでは独学のメリット・デメリットを整理します。
独学のメリットとデメリット
独学で合格を目指すメリットとしては、まず費用をかけないで済むことが挙げられます。通信講座やスクールの受講料は数万円〜十数万円が相場です。なるべくお金をかけたくない、ということであれば独学で勉強を進めていくしかありません。そうなると、必然的に自分のペースで学習を進めていくことになります。この点も、人によってはメリットと感じるでしょう。仕事を終えて帰宅したあとや通勤中などの隙間時間に、自分の生活リズムのなかで勉強を進められます。
また、独学の大きなメリットとしては、勉強のプランそのものを自分で考えることによって、学習への意識が高まるという点もあります。手探りで学習を進めていくため遠回りになるかもしれませんが、その分だけ理解も定着しやすく、学んだ内容を趣味や実務にすぐに役立てられるでしょう。
反対に、上記のメリットが、そのままデメリットにもなりえます。通信講座やスクールは、独学でつまづくポイントを押さえたカリキュラム、講師のアドバイスなどによって、スムーズに学習を進めることができます。つまり、費用をかけることで、余計な回り道をせずに効果的に学習を進めることができます。
また、色彩検定の1級は1次試験(マークシート)と二次試験(配色実技)に分かれていて、後者の練習は一人ではやや苦労します。配色実技は、出題に応じて、目的に沿った色を選んで説明することです。回答用紙に色票を貼り、カラーコードなどを書き込んでいきます。この実技に関して、過去問題が少ないことから独学では練習量がどうしても減ってしまいますし、「これで合っているのか」と確認するのも難しいです。
独学が向いている人・向いていない人の特徴
独学で色彩検定1級を目指すなら、3級と2級をすでに合格し、内容をしっかり把握していることが欠かせません。3~1級まで併願もできますが、独学で合格を目指すのであれば、しっかり勉強するためにも1級だけ別で受験したほうが合格率も高まると思います。
自分でペース配分して、問題集を解いて間違いを確認できる方、色彩検定1級をとって仕事や趣味に活かしている自分像をイメージできる方(モチベーションを保って学習を進められる方)は、独学が向いている(独学でも合格を目指せる)と言えるでしょう。
一方、講師に質問できたり、友人や仲間と一緒に学べる環境のほうがモチベーションがあがるようでしたら、独学よりも講座を受講した方が良いかもしれません。仮に3級、2級を合格済みであっても、自分では気づいていない苦手な分野が隠れていることもあるでしょう。
たとえば、ファッションや繊維関連の色彩知識は十分に習得しているものの、照明の専門用語や単位に関する知識は弱い、など。そういった苦手分野についての気づきも、一緒に学んでいれば発見しやすいかもしれないです。
スクールや通信講座を活用すべきケース
結論として、仕事で即戦力として色彩の知識が必要な方、短期間で確実に合格したい方、実技(配色カードなど)の練習を一人でするのが不安な方はスクールや通信講座を活用すべきでしょう。
色彩検定1級に合格するための勉強スケジュール
色彩検定1級は、1次試験(知識)と2次試験(実技)があり、範囲も膨大です。そのため、計画的な学習が不可欠です。以下に、学習の簡単なスケジュール感をまとめてみました。
半年前からの学習スケジュール例
6か月前〜4か月前
- 公式テキストを通読し全体像を把握
- 分野ごとにノートを作成し、基礎固め
3か月前〜2か月前
- 過去問に挑戦し、出題傾向を掴む
- 苦手分野を集中的に学習
- 二次試験の配色カード演習を開始
1か月前〜試験直前
- 過去問を繰り返し解く
- 模擬試験形式で時間配分を意識
- 二次試験の実技を毎日練習
この半年間の一連の流れは、あくまで一般的な学習のイメージです。人によって配分は異なるでしょう。ただ、誰にでも共通して言えることは、公式テキストの通読がもっとも大切ということ、そして1級ならではの実技試験を突破するため、配色カードをとにかく触って実際にコーディネートを作ってみてください。
直前期に重点を置くべき分野
- 照明、色彩心理、マンセル表色系
- 配色技法(トーン別・イメージ別配色)
- 実技のカード配列スピードを上げる練習
重点を置くべき分野は人それぞれだと思いますが、特に用語が難解な照明や視覚まつわることや、表色系についてはしっかりテキストを読み込んでください。配色技法については、トーン、イメージごとの違いをすべてしっかり理解しておくことが大切です。
日々の学習習慣の作り方
- 毎日30分〜1時間は色彩の勉強時間を確保
- 通勤中は暗記カードやアプリを活用
- 週末は実技練習やまとめ学習に充てる
自分の生活サイクルのなかで、最適なプランを立ててください。勉強しはじめはモチベーションも高いので一気に詰め込みがちですが、張り切りすぎても途中でガス欠になってしまいます。毎日淡々と、無理なく学べる範囲で計画を作りましょう。
効果的な勉強方法と学習のコツ
ここからは、独学で成果を出すための具体的な勉強法を紹介します。
公式テキストと問題集の活用法
- 公式テキストは隅々まで熟読(特に図表部分)
- 公式問題集は最低3回は繰り返す
- 間違えた問題はノートにまとめ、弱点克服
くどいようですが、とにかく公式テキストを熟読してください。これは3級や2級と変わりません。特に、テキストの「目次」をしっかり読み込んで、何を学ばないといけないのか、全体像を把握しましょう。独学で合格を目指すなら、出題範囲を知るためにも学習項目の整理が重要です。
範囲が広くて内容が多岐にわたっているため、1ページ目から毎日数ページ読み進めていくという読み方では、あまり効果的に記憶していけません。項目をしぼって通読し、その内容の「まとめ」を自分なりに作る習慣をしてみてください。
たとえば、「今日は表色系の項目を読んで整理しよう」「今日は色彩心理だ」「今日はエクステリアの色彩について」など、テーマを限定して、テキストのその箇所を読み、重要だと思うポイントをまとめます。
そして、問題集をひたすら解きましょう。出題傾向をつかみ、間違った分野を重点的に復習します。
配色や色彩理論の暗記を効率化する方法
- マンセル表色系を「縦軸・横軸・トーン」のイメージで暗記
- 配色のルールは、実際に色鉛筆やアプリで試しながら覚える
- 視覚的にインプットすることで暗記効率アップ
自分の理解度を測る効果的な方法として、テキストを見ずに、誰かにその内容を説明するつもりで書き出す、あるいは実際に説明する、という方法をオススメします。
公式テキストの目次だけを写真にとっておき、カフェでノートを開いて、その目次からどこかを選んで内容を覚えている範囲で書いてみましょう。すると、内容をうまく整理して書けない・説明できない(アウトプットできない)分野があることに気づきます。それは、その分野の理解がまだ乏しい証拠です。
さらに、配色実技の練習も進めていきます。まず市販の日本色研配色カードにPCCSの色番号を書いておき、カードの束を全部バラバラにはずして混ぜます。それから、色をみるだけで、どのトーンのどの番号かわかるようにゲーム感覚で繰り返し練習しましょう。また、配色カードの明度・彩度も、色をみただけで数字で把握できるようにしてください。

写真は、私が1級の勉強をしていたときのもの。配色カードそれぞれに各色のトーン、番号、明度、再度、慣用色名を書いて、ひたすら覚えました。
過去問演習を最大限に活かすコツ
- 出題傾向を分析し、頻出分野に優先的に取り組む
- 時間を計り、本番を想定して解く
- 解説を必ず確認し、知識を体系化する
試験日が近づいてきましたら、実際の試験時間を計って、1次試験、2次試験の過去問を解いてみます。
二次試験(実技)対策のポイント
- 配色カードを実際に切り貼りして練習
- 色のバランスを取るセンスを鍛える
- 制限時間内で解けるよう、繰り返し練習
実技については、配色カードを持ち歩いて、いつでも見直せるようにしましょう。トーンオントーンやカマイユ、ドミナントなど配色用語だけで、どの色を組み合わせたらよいか分かるようになるまで、反復あるのみです。
あとは、体調管理もお忘れなく。
独学で注意すべきポイント
独学は自由度が高い反面、落とし穴もあります。ここでは注意点を整理します。
モチベーションを保つ方法
- SNSや勉強仲間と学習進捗を共有
- 小さな目標(1週間で1章終えるなど)を設定
- ご褒美ルールで自分を励ます
学習の理解度をチェックする方法
- 過去問を模擬試験形式で解く
- 問題集を2回目以降は「答えを言葉で説明できるか」を意識
- 二次試験は第三者に配色を評価してもらう
独学の限界を感じたらどうする?
- 通信講座を一部だけ利用(模擬試験や添削サービスなど)
- オンライン動画でわからない分野を補強
- 書籍・資料を増やして多角的に学習
モチベーションをどうやって保つのかは人それぞれだと思いますが、3級と2級の併願は可能?の記事でも書きましたように、モチベーションについて考えすぎないことも大切です。気乗りしないときは思い切ってリフレッシュしましょう。
独学だと「知識が身についているのかな?」「正しい方向へ向かって学習を進められているのかな?」と不安になるかもしれません。その不安に打ち勝つ方法は、深く考えすぎずにテキストを読み、自分なりにまとめ、問題を解いて自分の理解度をチェックし、配色カードでコーディネートを作ってみる。このシンプルな繰り返しのみ。
学習の理解度をチェックする方法は、既述のとおり「内容をアウトプットできるか」で計ります。
試験は、結局のところテキストからしか出題されません。実技試験も、3級、2級、そして1級のなかで学んだ知識の組み合わせです。独学であれば、自分で考える力も同時にレベルアップしていくため、むしろ実技への対応力・知識の応用力は磨かれていくように思います。
どうしても難しさを覚えたら、講座を受けることも考えてみましょう。
独学合格を目指す人へのアドバイスまとめ
最後に、独学で合格を目指す方への総合的なアドバイスをお伝えします。
合格に必要な勉強時間の目安
- 目安は 300〜400時間
- 半年間、毎日2時間の勉強が理想
- 仕事や家庭と両立する場合は1年計画も現実的
いつ1級を受けるのかも考えよう
色彩検定は年に2回、夏期(6月)と冬期(11月)に実施されます。ただし1級は11月のみの開催で、11月の1次試験に合格した方のみ、12月の二次試験を受験できます。
そのため、夏期試験で3級と2級に合格したなら、その年の冬期に1級合格は十分に狙えます。一方、6月以降に「色彩検定を受けてみよう!」と思い立ったなら、その年の冬期にまとめて3級・2級・1級にチャレンジすることもできますが、かなりハードです。したがって、この場合は冬期に3級、翌年の夏期に2級、そして同年の冬期に1級に挑戦といった形で、余裕をもって進めたほうが無難です。
色彩検定1級は独学で合格できる?総括
色彩検定1級は確かに難易度が高い試験ですが、独学でも合格できます。大切なのは、長期的な学習スケジュールの立案、効率的なインプットとアウトプット、そして継続力です。この記事を参考に、自分に合った学習方法を取り入れて、合格への道を切り開いてください。
最後にもうひとつアドバイスを。私自身、独学で1級を合格しました。私はマイペースで学習を進めていけるタイプのため独学が性格にあっていましたが、たしかに一人では難しいと感じる部分もありました。ですから通信講座やスクールを受講したほうが効率的に学べるかもしれません。
「ただ単に1級の資格(肩書)が欲しいだけ」なのか、それとも「色を学ぶこと自体が楽しいのか?」と、自分の心に聞いてみてください。後者であれば、自然と学習を進められると思いますし、知識を趣味や仕事にすぐに活かせるようになるでしょう。
あなたの合格をお祈りしていますね。