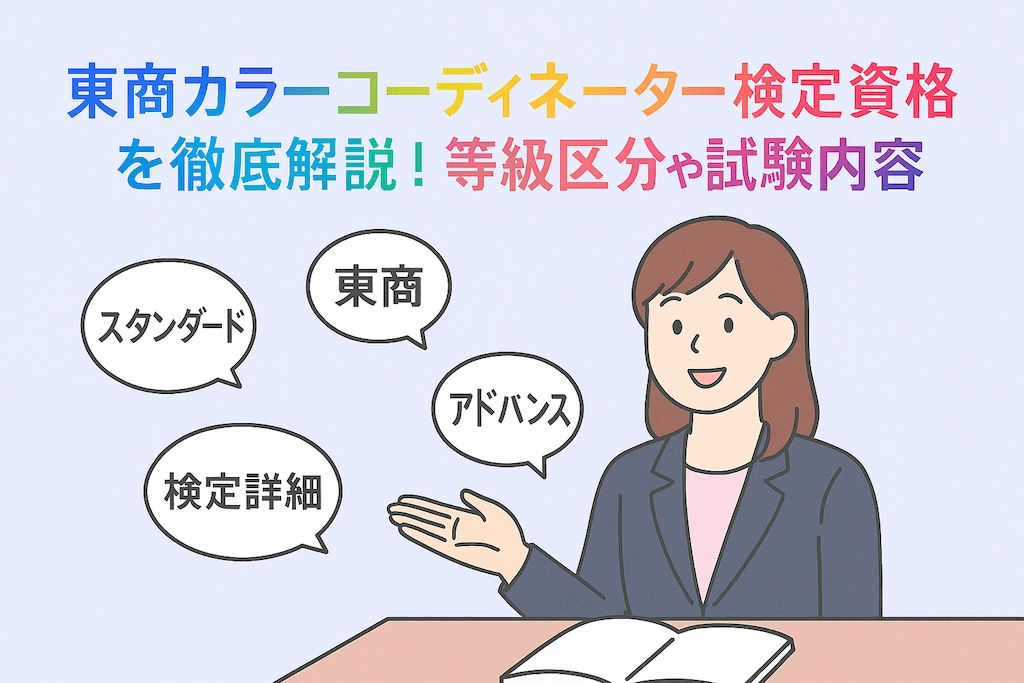「色彩検定と東商カラーコーディネーター検定ってどう違うの?」「試験内容や難易度は?」「資格を取るメリットはあるの?」と悩んでいませんか?
東京商工会議所が主催するカラーコーディネーター検定は、ビジネスシーンで“色を活かす力”を身につけたい人に向けた資格です。この記事では、等級ごとの特徴や試験内容、出題範囲、受験料や日程まで詳しく解説します。
東商カラーコーディネーター検定とは?

東商カラーコーディネーター検定は、東京商工会議所(通称:東商)が主催する資格です。1995年に第1回の試験が実施され、2025年で30年を迎えました。目的は「色彩の知識をビジネスや実生活に役立てる人材を育成すること」。ウェブサイトにも、「仕事に役立つ実践的な色彩の知識を学ぶことができる検定試験」と明記してあります。
ファッションやインテリアだけでなく、商品企画・広告・販促など、幅広い分野で活用できる実践的な色彩力を問われます。他の色彩資格(例:色彩検定)は理論面に強いのに対し、東商カラーコーディネーター検定は「実務やビジネス活用」にフォーカスしているのが特徴です。
東商カラーコーディネーター検定の等級区分と学べる内容
東商カラーコーディネーター検定は、現在 2つの等級区分 に分かれています。
スタンダードクラス
- 色彩の基礎知識を幅広く学ぶ初級レベル。
- 色の三属性、色相環、配色ルールなど、日常生活や仕事にすぐ役立つ内容。
- 「色を基礎から学びたい」「まずは入門レベルから挑戦したい」方におすすめ。
アドバンスクラス
- スタンダードクラスを踏まえ、実務的に使える応用力を問う中級レベル。
- 商品開発・店舗デザイン・広告戦略など、色を使った具体的な提案や企画に役立つ内容。
- 「色を仕事に直結させたい」「顧客に色の根拠を説明したい」人に最適。
東商カラーコーディネーター検定試験は、2020年に等級制度がリニューアルされ、現在の「スタンダードクラス」と「アドバンスクラス」の2つになりました。
このように3段階+1級3分割のシステムをとっていたのは、それだけ広範にわたる知識を求められる、難易度の高い試験だったためです。東商カラーコーディネーター検定は、色彩検定に比べると実務面の具体的な知識、たとえば商品色彩であれば、木の種類や表面加工の工法、樹脂(プラスティック等)の素材ごとの特徴や発色に関する内容まで出題されました。(色彩検定やパーソナルカラーではまったく触れない領域です)
従来までの3等級のカラーコーディネーター検定と、現在の「スタンダードクラス」と「アドバンスクラス」の2層制の検定の違いを公式テキストの中身で比較すると、スタンダードクラスは従来の3級〜2級に相当し、色の基礎知識や理論を学ぶ内容となっています。
そして、アドバンスクラスは1級相当です。スタンダードクラス以上に深い色への理解と、ビジュアルデザイン、ファッション、メイク・化粧品、インテリア、工業製品、環境といった各分野での色彩活用の知識を学ぶことができます。
東商カラーコーディネーター検定の出題範囲
東商カラーコーディネーター検定は、色の理論から実務知識まで出題されます。以下のリストは、公式テキストの目次から抜粋した「スタンダードクラス」と「アドバンスクラス」のそれぞれの出題範囲の一部です。
出題範囲の例
スタンダードクラスの中身についてザッと挙げますと、色とは何か、光と色の関係、色の三属性、色の名前、表色系(PCCS、マンセル表色系、CIE表色系、均等色空間)、配色の基本ルール、人が色を知覚する仕組み、心理効果、色を仕事に活かすための基礎、などの領域を学びます。
アドバンスクラスは、スタンダードクラスよりも高度な色彩知識と実務知識について出題されます。
たとえば、ビジュアルデザインと色彩の領域ではプレゼンのスライド資料の制作におけるカラーコーディネート、グラフィックやWEB制作における配色などが出題範囲です。
ファッションの色彩の範囲は、コーディネートタイプ別のイメージ、テキスタイル(繊維)ごとの特徴、配色調和論、ファッションの変化の歴史など。
化粧品の分野は、商品の色彩設計や管理について。インテリアは空間設計、工業製品は主に車のボディカラーに関してや、プロダクトデザインの変遷。環境色彩については守るべき各種法規や基準など。
このように、アドバンスクラスでは単に「色の理論を知っているか?」だけでなく、各領域において色彩を具体的にどう活かすか?活かされているのか?が問われます。
あなたがたとえば化粧品の販売員なら、メイクやファッションの領域は知識と関心を持っているでしょう。一方で、工業製品や環境の色彩法規などはまったくの専門外かもしれません。
そのような自分が普段関わりのない領域まで幅広く出題されるため、将来的にカラーコーディネーターとして活躍できる十分な知識を得ることができます。
試験方式・試験日程・受験資格・合格基準
東商カラーコーディネーター検定は現在、CBT方式とIBT方式の2種類の試験方式で受験することができます。
試験方式
カラーコーディネーター検定の受験者は、受験申し込みの際にいずれかを選択して受験します。出題形式は基本的に選択問題となります。CBT方式で受けてもIBT方式でも、もちろん出題内容は同じです。どちらも試験時間は90分。スタンダードクラスもアドバンスクラスも、いずれかの方式を選んで受験できます。
試験日程
東商カラーコーディネーター検定は、年2回 (第1シーズン・第2シーズン)実施されます。第1シーズンは夏期で、6月の下旬から7月上旬にかけて。第2シーズンは秋で、10月下旬から11月上旬の実施です。
CBT方式もIBT方式も試験日が完全に定まっているわけではなく、試験期間のなかから都合の良い日と開始時間を選んで受験することができます。
受験資格
学歴・性別・年齢・国籍などに一切制限はありません。また、東商カラーコーディネーター検定は「スタンダードクラス」と「アドバンスクラス」の併願受験も可能です。
受験料
受験料は等級ごとに異なります。
- スタンダードクラス:5,500円(税込)
- アドバンスクラス:7,700円(税込)
(※年度によって変更の可能性があるため、公式サイトの最新情報を確認してください)
CBT方式で受験する場合は、別途CBTの手数料2,200円(税込)も必要です。
合格基準
100点満点中、70点以上を取れば合格です。
受験を考えている方は、必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。
東商カラーコーディネーター検定の申込方法
カラーコーディネーター検定は、公式サイトから申し込みします。個人で受験する場合、公式サイトの申し込みページからCBT方式、IBT方式を選んでください。
いずれの受験においても、身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、第三者機関発行で原則として氏名、生年月日、顔写真が揃って確認できるもの)の原本が必要です。コピーは認められません。
CBT方式で申し込む場合は、公式サイトから受験サイトに移動してアカウントを作成し、試験を受ける会場と日時を選びます。そのあと、受験料を支払います。受験料の支払い方法は、クレジットカードかコンビニ決済です。申し込みが完了したら、メールで案内が届きます。
あとは当日に証明書や必要なものを持参して試験会場に向かい、指示に沿って受験します。
IBT方式を選ぶなら、自分のパソコンを用いて受験するため、パソコンの動作環境、試験を受ける場所、試験中の行動にルールが定められています。必ず事前にご確認ください。申し込みの流れはCBT方式とほとんど同じです。
企業や学校などで受験者が3人以上いる場合に適用される団体受験制度もありますので、ご担当の方は公式サイトからお問い合わせください。
色彩検定との違いは?両方の資格を同時受験はできる?
「色彩検定」と「カラーコーディネーター検定」は混同されがちですが、目的と方向性に違いがあります。
両資格の違いは?
- 色彩検定(AFT主催)
- 色彩理論を幅広く網羅。
- ファッション・インテリア・アートなど多方面に活用できる。
- 基礎から上級まで体系的に学べる。
- カラーコーディネーター検定(東商主催)
- ビジネスや実務に特化。
- 商品企画・広告戦略・空間デザインに直結。
- 実際の現場で「色をどう使うか」を重視。
まとめると:色の知識を「幅広く学びたい」なら色彩検定、「ビジネスや実務で活用したい」ならカラーコーディネーター検定が向いています。
色彩検定とカラーコーディネーター検定は、色の原理や色にまつわる基礎知識、理論などの領域においては学習内容は重複しています。一方で、色彩検定が色の理論や心理面で広範な知識を問う資格であるのに対し、カラーコーディネーター検定は各種のビジネス領域における色の活用や、一見すると色とは関係がないような専門用語まで頻出します。
両方とも最上級まで取得した身として、個人的な印象としては色彩検定の知識の方がアカデミック(学術的、学校で学ぶ内容)といったイメージで、カラーコーディネーター検定は仕事の現場で培った理解とノウハウ、といった違いを感じます。
両資格を同時に受験できる?
色彩検定とカラーコーディネーター検定は別団体が主催しているため、同じ年にまとめて受験することもできます。人によっては、そのほうが効率よく資格取得できるでしょう。
ただし、出題範囲が異なるため注意してください。色彩検定1級で学ぶ用語のいくつかは、カラーコーディネーター検定のスタンダードクラスで登場します。受験日までスケジュールに十分な余裕があるなら、しっかり学習計画を立てて進めてください。
東商カラーコーディネーター検定を受けるメリット
- 仕事に直結:販売促進や商品開発に強みを発揮できる。
- 説得力アップ:お客様や上司に色の根拠を論理的に説明できる。
- キャリアの武器になる:履歴書や資格欄に記載可能。
特に、マーケティングや営業、デザイン系の仕事をしている方にとっては、仕事に直結する即戦力資格と言えるでしょう。
資格を持っていることが就活・転職や仕事の現場において肩書として強みになるかどうかは、関わる領域によって異なると思います。しかし、カラーコーディネーター検定の受験において学ぶ内容は、間違いなくビジネスと社会生活に役立ちます。
色彩の専門知識を学んでいない人に比べると、色の扱い方には大きな差が出るでしょう。
まとめ|実務で色を活かしたいなら東商カラーコーディネーター検定
東商カラーコーディネーター検定は、ビジネスや生活に役立つ色彩の知識を実践的に学べる資格です。スタンダードクラスで基礎を固め、アドバンスクラスで応用力を磨けば、仕事や日常のさまざまな場面で「色のプロ」として活躍できます。
色を武器にキャリアアップを考えている方は、ぜひ挑戦してみてください!